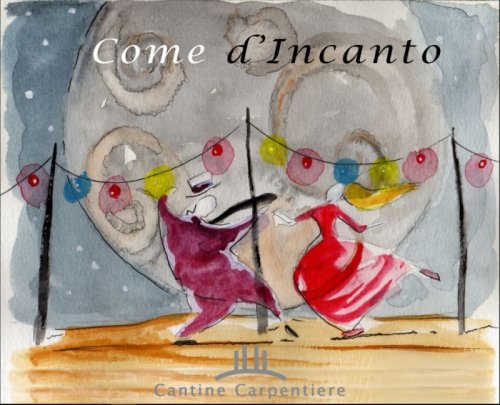ワインが食事するために置かれている役割を日々考えています。
食べ物の味わいにワインの味わいを重ねていくのか、食材の味わいを引き立てるようにワインの味をわき役にするのか。
いろいろな味わいの食べ合わせのパターンがあります。
その中で最近よく考えさせられるのは辛味とワイン。
辛味とは具体的には唐辛子。ワインがこれまで入ってなかった料理の世界、メキシカン、トルコ料理、韓国料理、中国料理などがありますがそれらに共通する食材として唐辛子があります。ここにワインを合わせるのは難しいと思われています。
そういう時に参考になるのは地図と歴史。
唐辛子とぶどうが混じり合う地域と歴史を探せば、ペアリングのヒントがあるかもしれません。
原産地は中南米と言われていますが大航海時代にポルトガル人が各地に伝播したことによって、食文化に影響を与えたとされています。
16世紀にはオスマンやポルトガルを経由してヨーロッパに伝わったとされています。
そのルートを見てみるとバルカン半島、ギリシャ、イタリア、イベリア半島の料理にワインと相性の良い唐辛子を使った料理があるように思えます。
これらの地域のワインを試飲した時に共通して感じるのはワインの味わいの中にあるスパイス感。このスパイス感と辛さが良い相性を見せてくれるのではないでしょうか。
南イタリア、ギリシャ、ハンガリーにおすすめがあります。
その中で、南イタリアのカラブリア州のぶどう、ガリオッポを使ったチロ、
http://aquavitae.ocnk.net/product/35 は地元でも唐辛子を使った料理と良く合わせるシーンに出会いました。
チェリーの果実、なめらかなタンニンと辛さがうまくマッチします。この果実の凝縮感がすばらしく、現地では氷をいれて飲まれていることもありますがそれでも味わいが薄くなる感じがしないほどです。
寒い時は顔から汗が出るような辛い料理を食べたくなる時がありますがそんなときでも方時にグラスを置いてみるのもおもしろいものです。
よろしくお願いいたします。
Aqua Vitae
河合
http://aquavitae.ocnk.net
食べ物の味わいにワインの味わいを重ねていくのか、食材の味わいを引き立てるようにワインの味をわき役にするのか。
いろいろな味わいの食べ合わせのパターンがあります。
その中で最近よく考えさせられるのは辛味とワイン。
辛味とは具体的には唐辛子。ワインがこれまで入ってなかった料理の世界、メキシカン、トルコ料理、韓国料理、中国料理などがありますがそれらに共通する食材として唐辛子があります。ここにワインを合わせるのは難しいと思われています。
そういう時に参考になるのは地図と歴史。
唐辛子とぶどうが混じり合う地域と歴史を探せば、ペアリングのヒントがあるかもしれません。
原産地は中南米と言われていますが大航海時代にポルトガル人が各地に伝播したことによって、食文化に影響を与えたとされています。
16世紀にはオスマンやポルトガルを経由してヨーロッパに伝わったとされています。
そのルートを見てみるとバルカン半島、ギリシャ、イタリア、イベリア半島の料理にワインと相性の良い唐辛子を使った料理があるように思えます。
これらの地域のワインを試飲した時に共通して感じるのはワインの味わいの中にあるスパイス感。このスパイス感と辛さが良い相性を見せてくれるのではないでしょうか。
南イタリア、ギリシャ、ハンガリーにおすすめがあります。
その中で、南イタリアのカラブリア州のぶどう、ガリオッポを使ったチロ、
http://aquavitae.ocnk.net/product/35 は地元でも唐辛子を使った料理と良く合わせるシーンに出会いました。
チェリーの果実、なめらかなタンニンと辛さがうまくマッチします。この果実の凝縮感がすばらしく、現地では氷をいれて飲まれていることもありますがそれでも味わいが薄くなる感じがしないほどです。
寒い時は顔から汗が出るような辛い料理を食べたくなる時がありますがそんなときでも方時にグラスを置いてみるのもおもしろいものです。
よろしくお願いいたします。
Aqua Vitae
河合
http://aquavitae.ocnk.net